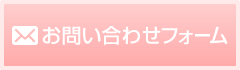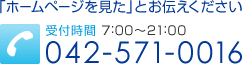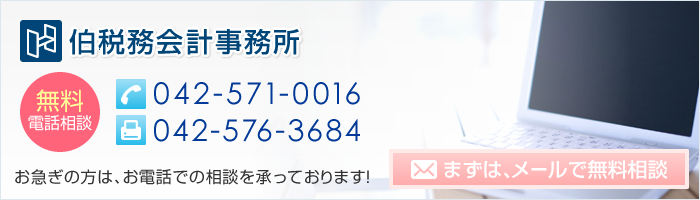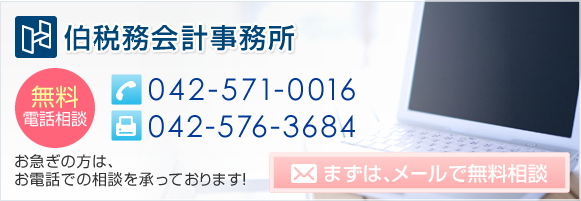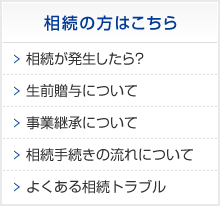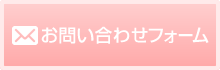【共働き世帯に効果的な節税方法とは】
2020.02.01更新
「小学生の子ども1人と夫婦の3人で暮らしています。共働きですが、子どもが大学に進学するまでに上手に貯めていけたらと思っています。できれば税金の負担を軽くしたいのですが、何か良い方法はあるでしょうか」という質問がありました。
最初に節税の基本について2つご紹介します。
1つ目は「所得控除」と「税額控除」です。
所得控除は税金を算出する前の所得を下げる方法です。
一方、税額控除は算出された所得税から税金そのものを控除する方法です。
そして2つ目は収入の多い人から優先して所得を減らすという方法です。
所得税は所得に税率を掛けて算出されますが、日本の課税制度では所得が高ければ高いほど税率は上がります。
そのためより節税になる方法としては、夫婦のうち収入の多いほうから先に所得を下げるのが得策です。
上記のような点から共働き世帯に効果的な節税方法としては「住宅ローンを夫婦で活用する」「医療費控除を受ける」などが代表的でしょう。
住宅ローン控除はそれぞれがローンを活用して税額控除を受けることができます。
医療費控除は生計を共にしている家族であれば、その世帯の医療費の合計額について所得の高い人がまとめて所得控除を受けるほうが効果的です。
この他にも「親を扶養に入れる」など節税方法は多いので上手に活用して将来設計をしましょう。
投稿者: