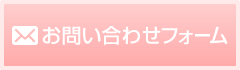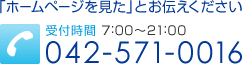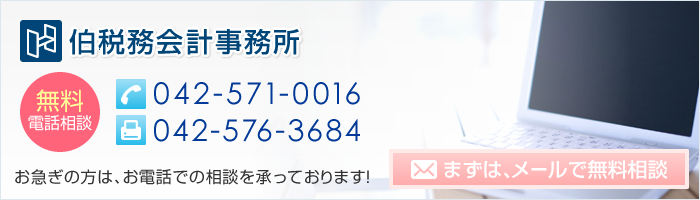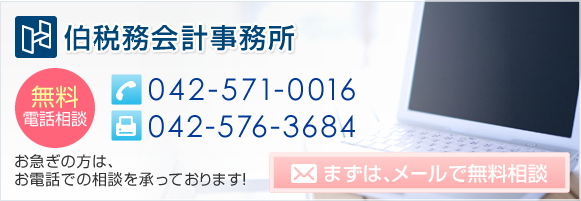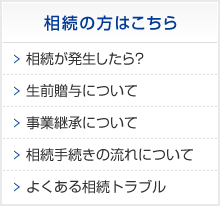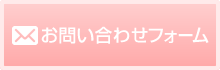【イートインは10%でテイクアウトは8%】
2018.07.01更新
来年の平成31年10月1日に消費税率は10%に引き上げられます。
引き上げの際には、特定の品目だけを8%に据え置く軽減税率制度も実施されます。
気になるその「特定の品目」ですが、酒類・外食を除く飲食料品と週2回以上発刊される新聞(定期購読契約に基づくもの)が対象になります。
例えば夕食用にスーパーマーケットで購入する肉や野菜、牛乳やパンなどは軽減税率の対象になります。
一方、レストランやハンバーガーショップなどのお店で飲食をした場合は、軽減税率は適用されません。
ただし、そこでテイクアウトしたハンバーガーなどは軽減税率が適用されます。
また宅配ピザで注文したピザなどは軽減税率が適用されますが、ケータリングを利用した場合は適用されません。
このように対象品目の線引きがさまざまなので購入者も混乱しそうですが、売る側のお店はそれ以上に混乱しそうです。
取り扱う商品などによっては、複数の税率を使い分けなければいけないケースも出てくることでしょう。
またそれによりレジや受発注システムを、新たに導入しなければいけなくなるかもしれません。
このような対応が必要になる中小企業や小規模事業者等には、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」という制度があります。
まだ1年以上ありますが、今から準備を進めていきましょう。
投稿者: