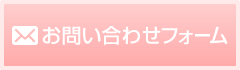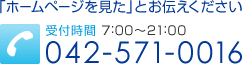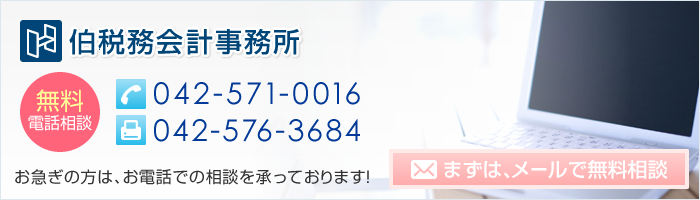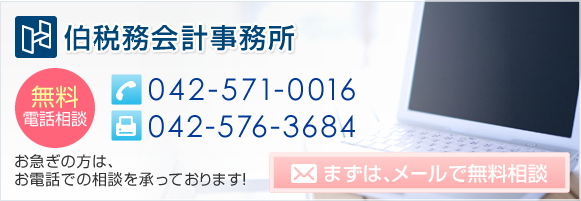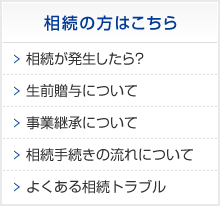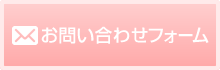【他社の役員給与と役員賞与】
2022.09.01更新
法人企業統計調査をご存知でしょうか。
これは営利法人などの企業活動の実態を把握するために、標本調査として実施されている統計法に基づく基幹統計調査のひとつです。
財務省の財務総合政策研究所が1948年以降、毎年行っている調査です。
この統計調査の中には、業種別・資本金階級別の役員賞与や役員給与の額があります。
2022年2月に最新年度である2020度の統計年報が発表されました。
金融・保険業を除いた全産業の平均役員給与は約466万円、平均役員賞与は約13万円でした。
全体による平均役員給与の上位5業種は、1位から純粋持株会社(約1220万円)、化学工業(約897万円)、非鉄金属製造業(約835万円)、自動車・同付属品製造業(約797万円)、鉄鋼業(約758万円)でした。
ちなみに純粋持株会社とは、自らは事業活動を行わず、主に子会社の指揮監督を目的とした会社のことです。
やはり資本金が大きいほど報酬の額も多くなる傾向にあり、全産業において資本金1000万円未満企業の平均役員給与が約358万円に対し、資本金10億円以上企業になると約1771万円となっています。
金融・保険業以外では58業種、金融・保険業については10業種でそれぞれの資本金階級別に集計されているため、ご覧いただければ自身の業種の状況がよく把握できるのではないでしょうか。
投稿者: