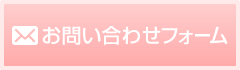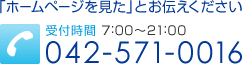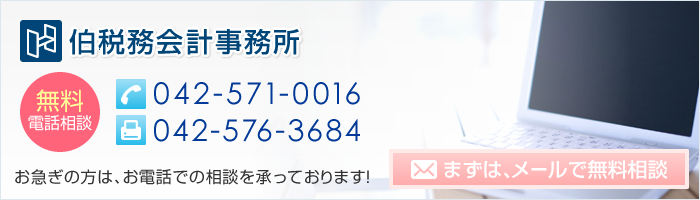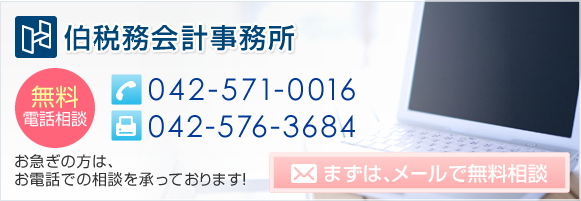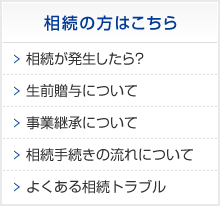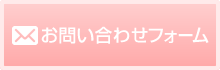2011.04.27更新
【かわいいペットにも税金が・・・】
・ドイツでは「犬税」という税金があり、年約1000~2万円程度が課されています。
・ヨーロッパではドイツ以外にもあり、街の清掃費などに使われている珍しくない税金です。
・今の日本で犬税と聞くとちょっと違和感を覚えます。
・しかし、古くは徳川綱吉が将軍だった江戸時代の日本でも「生類憐れみの令」が発令された際に「犬税」が徴収されていました。
・また、明治時代には飼い犬が急増して狂犬病が蔓延し、その対策として犬税が導入されたこともありました。
・これが昭和57年に廃止されるまで、最大で2686の自治体で徴収され、最後に廃止になった長野県四賀村では、1頭あたり年300円で約15万円の税収があったそうです。
・この他にも、明治の初期には国民が投機目的で競ってうさぎを飼い始めたために、1羽につき月1円という「うさぎ税」が導入されました。
・当時の1円は、お米が20~30kgくらい買える価値があったようです。
・このように税制は時代に応じて変化していることがわかります。
・一般社団法人ペットフード協会が発表している調査結果によると、国内の飼育頭数では犬が約1232万頭、猫が約1002万頭です。
・仮に1頭につき年1万円を課税すると税収は約2200億円になります。
・そのためか、現在の日本においても「ペット税」の導入を求める声も聞かれます。
国立市市で遺言・遺産相続でお悩みなら伯税務会計事務所へ
投稿者: 伯税務会計事務所
2011.03.13更新
【小規模企業共済加入を勧めたいのですが】
・左官業を営むある個人事業主から「あと3年で第一線から退きたいと思っています。後継者は、身内ではないのですが従業員の一人を考えています。そこで後継者候補の従業員に対して小規模企業共済に加入するよう勧めたいと思うのですが可能でしょうか?」というご質問がありました。
・身内でなくとも事業を継いでくれる人がいるということはとても心強く、また、その方への思いも格別でしょう。
・「小規模企業共済制度」とは、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておく制度で、小規模企業共済法に基づき国が全額出資している「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が運営しているものです。
・これまで個人事業においては事業主にしか加入が認められておらず、その配偶者や後継者の方は加入できませんでした。
・しかし、平成23年1月1日からは一定の要件を満たせば、配偶者や後継者、親族以外の方も共同経営者として「個人事業主1人につき"2人まで"」加入することができるようになりました。
・この共済制度のメリットは、共済金が「退職所得扱い」となること。
・また、掛金は毎月1000円~7万円の範囲内で自由に選べ「全額所得控除の対象」となることです。
・今回のケースでは、共同経営者という形で要件を満たせば共済に加入することができます。
立川市・国分寺市で相続の得意な税理士をお探しなら伯税務会計事務所
投稿者: 伯税務会計事務所
2011.02.05更新
【所得税が還付されるかもしれません】
・「遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象とならない」とする最高裁判所の判決が昨年ありました。
・これにより、過去に遡って納めすぎていた所得税が還付されます。
・具体的なケースの一例としては、亡くなられたご主人の生命保険金をその遺族が年金形式で受け取っているような場合。
・これまでは年金として受け取った保険金は、「各年ごとに年金収入から、それに対応する支払保険料を差し引いた金額」が所得税の対象となっていました。
・しかし、今回の判決により「年金として受け取った各年の保険金を、所得税の課税部分と非課税部分に振り分けて課税する」ように変更されました。
・そのため非課税部分については、過去に遡って税金が還付されることになりました。
・該当者については保険会社などから連絡があるようですが、住所が変わってわからなくなっている場合などは通知が来ないおそれもあります。
・そのため該当していそうな方は確認されることをお勧めします。
・また、所得税の他にも住民税や国民健康保険などの社会保険関係、扶養控除関係にまでも影響を及ぼす場合もあります。
・その際には、自分で申告をしないと還付されませんが計算方法など複雑です。
・ですから、少しでも「該当するかな?」と思われた場合には遠慮なくご相談ください。
投稿者: 伯税務会計事務所
2011.01.14更新
【サラリーマンでも確定申告が必要な場合とは?】
・サラリーマンは自分自身でやらなくても、毎月の給料から税金が天引きされ、年の暮れには自動的に年末調整が行われます。
・しかし、サラリーマンであっても、確定申告が必要な場合もあります。
・また、それにより税金が戻ってくることもあるのです。
・例えば、副業があります。
・昔は認められなかった副業も、長引く不況のため最近は認めている会社も多いようです。
・会社が終わった後の数時間や土曜日、日曜日だけ働くといった場合、副業先の収入はそれほど多くはないかもしれません。
・しかし、主となる会社と副業先の2ヶ所から給与をもらうことになるため、その2つを合算し確定申告をしなければなりません。
・また、趣味のホームページから広告収入などがある場合、これは雑所得という分類になります。
・この場合、年間の所得(収入から経費を引いた正味の儲け)が20万円を超えると確定申告が必要となります。
・20万円以下であれば確定申告は不要なのですが、仮に所得税が源泉されるような収入であれば、場合によっては確定申告をすると源泉されていた所得税が戻ってくることもあります。
・ただし、その場合は、確定申告をすることにより住民税は上がります。
・そのため「戻ってくる所得税分」と「上がる住民税分」を的確に計算しないと、逆に損するおそれもありますので注意が必要となります。
投稿者: 伯税務会計事務所
2010.12.12更新
【納税額が間違っていたことに気がついたら?】
・誤って税金を多く納めていたり、もしくは少なく納めていたことに気がついた場合、どのように対処すればよいでしょうか?
・現在、所得税や法人税など多くの税金は、納税者自らが計算をして納める、いわゆる「申告納税制度」という方法がとられています。
・計算間違いなどで税金が正しく納められていなかった場合には、訂正をすることになるのですが、「多く納めていた場合」と「少なく納めていた場合」とでは訂正の仕方が異なります。
・まず、「多く納めていた場合」は、「更正の請求書」という書類に訂正事項を記載して提出します。
・その際の注意点は、原則として申告の期限から1年以内でなければならないということです。
・つまり、何年か経過したあとに多く納めていた事実に気がついても、原則として税務署は受け付けてくれません。
・一方、「少なく納めていた場合」は、「修正申告書」を提出して不足している税金を納めることになります。
・少し不平等に感じられるかもしれませんが、修正申告の場合は、更正の請求のような1年以内という期限はありません。
・なお、「更正の請求」「修正申告」のいずれも国税通則法に沿って、基本的に本来の税金とは別に利息(還付加算金・延滞税)が発生します。
投稿者: 伯税務会計事務所
2010.11.07更新
【ご存知ですか?「もしも」のときのこんな制度】
・取引先の不測の事態は、できることなら避けて通りたいものです。しかし、商売を営む上では、なかなか避けて通ることはできません。
・回収困難となった売掛金が小額であれば、それが事業継続に及ぼす影響は小さいでしょう。
・しかし、もしも多額の売掛金が回収できない状況になったら、事業継続は難しくなり、連鎖倒産という最悪の事態に陥るかもしれません。
・このような「もしも」のときの資金調達として、『中小企業倒産防止共済』という制度があります。
・これは国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構というところが運営をしています。
・毎月5千円から8万円の範囲で積み立てを行い、現状では320万円(掛金の40倍で掛け止めも可)まで積み立てられます。
・またメリットとして、掛金は税法上、経費または損金とすることができます。
・そして一番気になる「もしも」のときには、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3200万円)で、回収が困難となった売掛金債権等の額以内の「貸付け」が受けられます。
・しかも、「無担保」「無保証人」「無利子」で借り入れることができます。
・財務状況や返済能力などによる金融審査での借り入れではないので、「もしも」のときに役立つ制度です。用心するに越したことはないですね。
投稿者: 伯税務会計事務所
2010.10.02更新
【もしかして私のケースも相続税の対象に?】
・相続や遺贈(いぞう)によって得た、居住用または事業用に使用されていた宅地等。
・これらは、一定の要件に該当する宅地であれば、相続税の負担を軽減させる「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができます。
・しかし、これが平成22年4月1日から改正され、適用要件が厳しくなりました。
・例えば、被続人(亡くなった人)が住んでいた180平米の宅地があったとします。この宅地の評価額が1億円。
・相続人は子供1人だけで自宅を持って別居していた場合、従来は別居であっても、200平米までは50%の評価減を受けることができたので、相続税の評価額は5000万円でした。
・しかし、改正後は「相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等であること。」と改正されました。
・つまり、例のように自宅を持って別居していた子供が相続した場合、軽減措置はなくそのまま1億円の評価額となってしまうのです。
・その他にも、共同相続があった場合の適用要件等の改正もありました。
・改正前までの相続税では「小規模宅地等の特例」を利用することで基礎控除枠に収めることができ、納税負担が生じないケースも少なくありませんでした。
・今回の改正は、そのような点にも影響する可能性があるので注意が必要です。
投稿者: 伯税務会計事務所
2010.09.26更新
【ハンバーガーをテイクアウトして節税に】
・深刻な財政赤字のため、いよいよ消費税に関する議論が活発になってきました。現在、日本の消費税率は、非課税のものを除いてすべて一律5%です。今後これが、引き上げられていきそうな気配です。
・そうなると問題になるのが、「所得に対する逆進性」です。これは、税率が上がると所得が低い人ほど「収入に対する消費税の割合」が大きくなるという考え方です。
・そのため消費税率の高い国々では、食料品などの生活必需品等については税率を低く抑える「複数税率」を採用しているところが多くありますが、その課税方法は様々です。
・例えばイギリスでは、食料品の税率は0%でも温かい商品などは17.5%になります。
・また、ドイツではハンバーガーをお店で食べると税率は19%ですが、持ち帰れば7%になります。さらにフランスではキャビアが19.6%でトリュフは5.5%と定められています。
・このように複数税率は、同じ商品なのにどこで食べるかで税率が異なったり、食料品の種類や状況によって細かく分類されて非常に複雑です。
・そのため日本では、消費税率を引き上げた場合、複数税率にするのか、はたまた現状のように一律税率のままで、所得の低い人には食料品などの支出に掛かった消費税分を払い戻す方法にするのかが議論がされています。
投稿者: 伯税務会計事務所
2010.08.15更新
【墓地購入のタイミングで相続税額が変わる!?】
・相続は亡くなった人の預貯金、有価証券、土地建物など「プラスの財産」だけでなく、借入金などの「マイナスの財産」も同時に引き継ぎます。
・この「プラスの財産」から「マイナスの財産」を差し引いた残りが、相続税の「基礎控除額」を超えると基本的に相続税が発生します。(基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数)
・「プラスの財産」の中には、非課税のものもいくつか含まれます。
・その1つに、墓地や墓石、仏壇、仏具などの祭祀財産があります。それが純金製の仏壇や仏具であっても、「骨とう的価値があるなど投資の対象となるもの」「商品として所有しているもの」でないと判断されれば非課税となります。
・また、生前に墓地の購入を済ませておけば、その分、「プラスの財産」が減少して相続税を減らすことができます。
・この場合のポイントは、「相続が発生するまでに代金の支払いを完了しておく」ことです。
・支払いをしていないからと「マイナスの財産」として、「プラスの財産」から差し引けそうですが、祭祀財産の未払い分は相続財産から控除することはできないため注意が必要です。
・なお、葬式の費用は債務(マイナスの財産)ではありませんが、相続税を計算するときは「プラスの財産」から差し引くことができます。
投稿者: 伯税務会計事務所
2010.07.02更新
【法人税率0%の地域に会社を移したら?】
・世界の法人税率は、最も水準の高い40%台の日本やアメリカなどをはじめ、なんと0%のケイマン諸島などまで幅広くあります。
・「じゃあ、法人税が無いケイマン諸島に会社を移そうかな...」と、真剣に考えたくなりますね。
・日本では、「国内に本店、もしくは主となる事務所がある法人」のことを「内国法人」と呼んでいます。
・逆に、「国内に本店、もしくは主となる事務所がない法人」のことを「外国法人」と呼んでいます。内国法人の場合、国内はもちろんのこと海外支店を通じて得た所得も、日本での課税対象になります。つまり、日本に本社のある会社が、法人税率0%のケイマン諸島に支店をつくり、ケイマン諸島で所得を得たとしても、その分も含めて日本の高い法人税率で課税されることになります。
・では逆に、ケイマン諸島に本社を置き、日本に支店をもつ外国法人をつくったとします。この場合、日本支店が得た所得は、ケイマン諸島の法人税率0%が適用され「法人税は不要」かと言えばそうはなりません。外国法人の場合は、「日本で生じた所得に対してのみ」日本の法人税率で課税されるのです。
・つまり、内国法人でも外国法人でも、日本で商売をして得た所得は、日本の高い法人税率から逃れることはできないということですね。
投稿者: 伯税務会計事務所