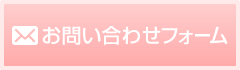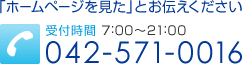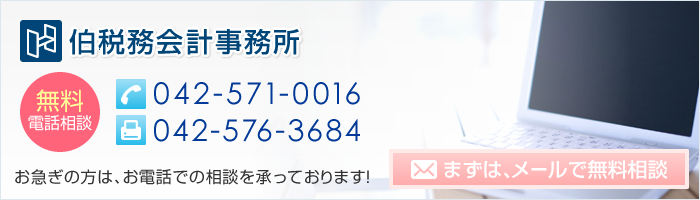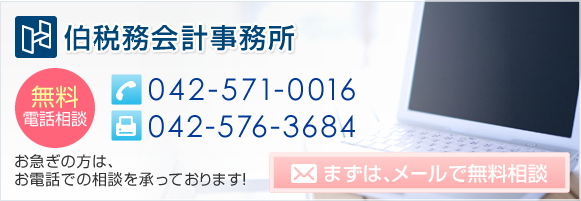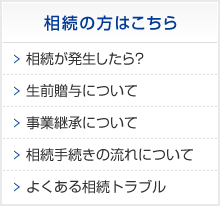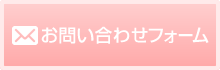2015.03.01更新
消費税の課税対象になる取引は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と外国貨物の輸入」となります。
つまり、事業者が日本国内で商品の販売やサービスを提供する場合などには、原則として消費税がかかることになります。
では、国外と取引をする場合はどうなるのでしょうか。例えば、商品などを国外に販売する輸出取引の場合には、その輸出にかかる消費税は免除されます。これは「内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しない」という考えに基づくものです。
私たちの身近なところでは免税店があります。海外に行く際に免税店でお土産などを買う場合には、いくつかの条件を満たせば消費税が免除されます。事業者の場合は、商品の輸出や国際輸送、国際電話などがあります。
例えば、自動車メーカーが国内において自動車を販売する場合には消費税が課税されますが、輸出をする場合は免税となります。このように輸出取引は消費税が免除されますが、これに使用する部品の仕入れなどには消費税が含まれていることになります。
そのため輸出の場合には、これらの経費に含まれる消費税および地方消費税の額は、申告の際に仕入税額の控除をすることができます。なお輸出免税の適用を受けるためには、輸出許可書などの必要書類を保管しておく必要があります。
投稿者: 伯税務会計事務所
2015.02.01更新
日本の法人税の実効税率は、欧州やアジア各国に比べて高い水準にあります。この税率を引き下げるためには、別の財源確保が必要だとされています。
そして、その代わりの財源確保のひとつとして挙げられるのが、法人事業税の「外形標準課税の対象拡大」です。企業はその活動をするにあたり、地方自治体より道路や防災、警察など各種の行政サービスを受けています。
法人事業税は、「この経費を企業が分担するべきである」という考えにもとづく地方税です。行政サービスは黒字企業も赤字企業も受けています。
そのため、ほとんどを黒字企業で負担している「事業所得だけを基準とする従来の方式」ではなく、赤字企業も負担する「事業規模などに応じて課税する外形標準課税」は、より公平に税を負担する制度とも考えられています。
外形標準課税制度は平成15年度の税制改正で創設され、平成16年4月1日以後開始の事業年度から適用されています。
現在この制度の対象になるのは、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人です。ただし、これまでの所得課税法人に限るものとし、公共法人等、人格のない社団等、特別法人などは除かれます。
新たな財源確保のためにこの対象を中小企業にまで拡大することは、「中小企業の新たな負担となり地域経済に悪影響が及ぶ」と心配する声も出ています。
投稿者: 伯税務会計事務所
2015.01.05更新
「国税庁から民間給与実態統計調査票というものが届いたのですが、民間給与実態統計調査とは一体どんなものなのでしょうか?また、調査票の提出は義務なのでしょうか?」というご質問がありました。
「民間給与実態統計調査」は、民間給与実態統計の作成を目的とした調査です。民間給与実態統計は、民間の事業所における年間の給与の実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別などに明らかにします。
さらに租税収入の見積りや租税負担の検討、税務行政運営などの基本資料とすることを目的としています。
対象になるのは、各年の12月31日現在で民間の事業所に勤務している給与所得者で、所得税の納税の有無は関係ありません。
特色は、従事員1人から5000人以上の事業所まで広く調査していることや、給与階級別、性別、年齢階層別、勤続年数別による給与所得者の分布が分かることなどです。
なお、調査票が届く事業所は平成24年分の場合は、従業員数1~9人の事業所では400分の1、10~29人では200分の1、30~99人では60分の1といった抽出率になっています。
最後に調査票の提出についてですが、国の重要な統計調査である基幹統計調査を行う場合には、「報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない」と統計法第13条で規定されていて報告義務が課されています。
投稿者: 伯税務会計事務所
2014.12.01更新
「社会保障・税番号制度」というとピンとこないかもしれませんが、「マイナンバー制度」というと耳にされたことがある方も多いのではないでしょうか。
この制度には、「複数の機関に存在する特定の個人の情報」を同じ個人の情報であると確認することにより、社会保障と税制度の効率性や透明性を高める目的があります。
そのため、住民票を持つすべての人に1人1つの番号が指定されます。これを「マイナンバー」といいます。
「社会保障・税・災害対策」の分野において、国の行政機関や地方公共団体などは保有する個人情報とマイナンバーを紐づけて効率的に情報管理が行え、さらには関係機関との間で迅速かつ確実にやり取りができるようになるといわれています。
マイナンバーは、平成27年10月から市区町村より「通知カード」が送付され、平成28年1月から「社会保障・税・災害対策」の行政手続で必要になります。
なお、国の行政機関などだけでなく民間企業でも、従業員の給料から源泉徴収をして税金を納めたり、健康保険や厚生年金の加入手続を行ったりする際に、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取り扱うことになります。
また、外部の人に講演を依頼して報酬を支払う場合には、報酬から税金の源泉徴収が必要となります。このような場合にもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
投稿者: 伯税務会計事務所
2014.11.01更新
贈与税の課税方法には「暦年課税」や「相続時精算課税」がありますが、今回は税率構造が変わる暦年課税についてお話をします。
暦年課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。そして、その合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた課税価格に、一定の税率を掛けるなどして税額を算出します。
税率は基礎控除後の課税価格によって異なり、現状では6段階で段階により10~50%の税率に分けられています。
それが平成27年1月1日から8段階になり税率が10~55%になります。
また、改正後は一般贈与財産は「一般税率」が、特例贈与財産には「特例税率」が適用されることになります。
特例税率が適用されるのは、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により財産を取得した場合で、その財産を取得した人が「財産の贈与」を受けた年の1月1日において20歳以上である場合となります。なお、特例税率に該当しない場合は一般税率となります。
どちらも最低と最高の税率は同じですが、特例税率は一般税率に比べて税率の上がり方が緩やかです。
例えば贈与額が600万円だった場合、一般税率では30%であるのに対して特例税率は20%となります。このため贈与税は、一般税率が82万円なのに対して特例税率は68万円と、その差が14万円になります。
投稿者: 伯税務会計事務所
2014.10.01更新
平成20年にはじまった「ふるさと納税」ですが、当初に比べて特産品などの特典が充実してきたこともあり注目度が高まっているようです。そこでもう一度、どのような制度なのかを見てみましょう。
まずはじめに、ふるさと納税には「納税」という言葉がありますが、実際には都道府県や市区町村に対する寄附になります。
また、寄附をする先の「ふるさと」に定義はなく、お世話になったところや応援したいところなど、自由に寄附をする都道府県や市区町村を選ぶことができます。
寄附をした場合、寄附額のうち2000円を超える部分について一定限度額まで原則として全額が、所得税と住民税から控除されます。
なお、一定限度額は個々の条件により異なりますが、住民税の10%程度がひとつの目安となります。
手順は、まず希望する都道府県や市区町村へ寄附を行います。そして、寄附を行った年の翌年に確定申告をすることで、寄附額に応じて所得税と住民税から控除されるという流れになります。
ふるさと納税のメリットは、生まれ故郷など希望する都道府県や市区町村に寄附をして応援できることや、寄附額に応じた特産品や優待券などの特典があることでしょう。
一方のデメリットには、所得税や住民税の軽減を受けるためには確定申告が必要なことや、最低でも2000円は自己負担となることなどが挙げられます。
投稿者: 伯税務会計事務所
2014.09.01更新
これまでは原則として、法人が支出した交際費等については損金不算入でした。ただし、資本金1億円以下の中小法人の場合は、800万円以下の交際費等について全額損金算入が認められていました。
この「交際費等の損金不算入制度」が改正され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることになりました。
まずはじめに、1人あたり5000円以下の飲食等のために要する費用においては、書類の保存要件を満たしているものについては、これまでどおり全額損金算入が認められています。
次に5000円を超える場合ですが、資本金1億円以下の中小法人以外の大企業など、これまで交際費等の全額が損金不算入だった法人においても、接待飲食費の額の50%相当額が損金算入できることになりました。ただし、従業員や親族などに対するものは除かれるのでご注意ください。
また、資本金1億円以下の中小法人においは、前述の「接待飲食費の額の50%相当額の損金算入」か「定額控除限度額までの損金算入」のいずれかを選択できることになりました。
なお、接待飲食費は、飲食等の「年月日・参加した得意先等の名称とその関係・参加した者の数・その費用の金額並びに飲食店等の名称および所在地」などを帳簿書類に記載しておく必要がありますので、きちんと整理保存しておきましょう。
投稿者: 伯税務会計事務所
2014.08.01更新
飛鳥時代の701年に完成した大宝律令では、「耕地の広さに応じて稲を納める税」や「その土地の特産物を納める税」など、租・庸・調という税の仕組みができました。
室町時代は米などの年貢が税の中心でした。また、街道に設けられた関所では、通行税の関銭などが税として課せられました。
安土桃山時代は豊臣秀吉が太閤検地を行い、農地の面積だけでなく収穫高なども調べて年貢を納めさせるようにしました。
江戸時代には、当時の営業税や営業免許税にあたる運上金・冥加金を、商工業者などに課税するようになりました。
明治時代になると政府は、歳入の安定を図るために地租改正を実施します。地券を発行して土地の所有者を確定し納税義務を課しました。そして、課税の基準を従来の収穫量から地価に改め、地租として貨幣で納めるようにしました。また、所得税や法人税が導入されたのもこの頃です。
現在ある税の仕組みができはじめたのは大正時代から昭和初期にかけてで、1940年(昭和15年)には源泉徴収制度が採用されました。
1989年(平成元年)には消費税が導入されます。当初の税率は3%でしたが1997年には5%に、そして2014年の今年に8%となりました。
このように税の制度は、社会の変化にともない変わってきました。そして、これからもまた変わっていくことでしょう。
投稿者: 伯税務会計事務所
2014.07.01更新
「先日、住宅ローン控除が4月から増えたということを知りました。
そこで、どのように変わったのか教えてください」というご質問がありました。ご質問の住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて新築または増改築をした場合などに、一定の要件を満たせば所得税や住民税の控除の適用を受けることができる制度です。
具体的には、毎年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が、10年間に渡って最大控除額を限度に控除されます。今回はその「最大控除額」が増えました。
一般住宅の場合は、平成26年3月までの最大控除額は200万円(年間20万円×10年)でしたが、平成26年4月から平成29年末までの最大控除額は400万円(年間40万円×10年)に増えました。
また、長期優良住宅と低炭素住宅については、最大控除額300万円(年間30万円×10年)から500万円(年間50万円×10年)に増えました。
さらに、所得税から控除しきれなかった場合には住民税から一部控除ができますが、その控除上限額も年間9.75万円から年間13.65万円に引き上げられました。
なお、経過措置により5%の消費税率が適用される場合や、消費税の課税対象とならない中古住宅の個人間売買などは、平成26年4月以降であっても平成26年3月までの措置が適用されます。
投稿者: 伯税務会計事務所
2014.06.01更新
特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合に、その取得価格の30%を特別償却することができる特別償却制度というものがあります。
これは、青色申告書を提出する中小企業者等が、認定経営革新等支援機関による経営改善に関する指導および助言を受けて、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に設備を実際に取得し、営む商業、サービス業等の事業のために使用する場合に適用される制度です。
「商業、サービス業」には、卸売業、小売業、情報通信業、損害保険代理業、不動産取引業、自動車整備業、農業など、その他にも多くの事業が該当します。
また「中小企業者等」とは、常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者、資本金の額が1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く)、中小企業等協同組合などになります。
そして認定経営革新等支援機関には、認定を受けた税理士や金融機関、商工会議所などがあります。
なお、個人事業者または資本金3000万円以下の法人においては、「取得価格の30%の特別償却」か「取得価格の7%の税額控除」のいずれかを選択することができます。
ただし税額控除の場合は、「取得価格の7%」または「事業所得に係る所得税額または法人税額の20%」のいずれか低い額になり、税額控除限度の超過額は1年間繰越すことができます。
投稿者: 伯税務会計事務所