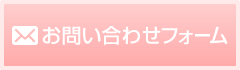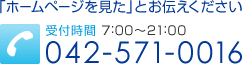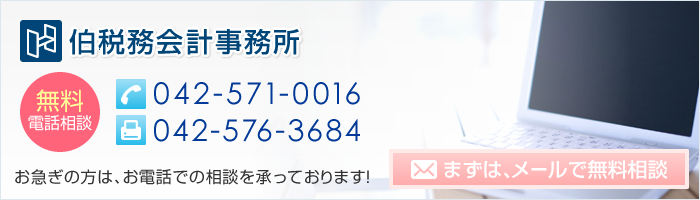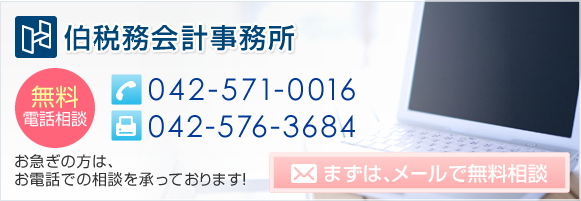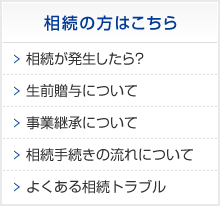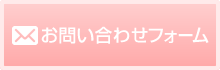【「私」か「私たち」か】
2023.08.15更新
昭和という時代は、松下幸之助、本田宗一郎、稲盛和夫といった名経営者が活躍した一方、もう昭和の商売の常識はなかなか通用しないともいわれます。
明暗を分けるのは時代ではなく、個々の人間性であるのは言うまでもありません。
「ボス」と「リーダー」の違いを端的に言語化した、イギリスの高級百貨店チェーン「セルフリッジズ」の創業者ハリー・ゴードン・セルフリッジの言葉を引用してみましょう。
ボスは「私」と言うが、リーダーは「私たち」と言う。
ボスは失敗の責任を追及するが、リーダーは失敗の後始末をする(失敗から学ばせる)。
ボスはやり方を知っているが、リーダーはやり方を教える(人を育てる)。
ボスは恐怖をあおるが、リーダーは熱意を持たせる。
ボスは時間通りに来いと言うが、リーダーは自ら時間前にやってくる。
ボスは仕事を苦役に変えるが、リーダーは仕事をゲームに変える。
ボスは間違いを非難するが、リーダーは間違いを改善する。
ボスは権威に頼るが、リーダーは志をより所にする。
ボスは「やれ」と命令するが、リーダーは「やろう」と言う(導く)。
言われてみれば納得のことばかり。
襟を正すことはあっても、そこに新しい発見はありません。
しかしこれらの言葉が、今から100年前に言われたものだとしたら、身に染み方が少し変わってくる気がします。
100年前から言われていることが今の時代でも通用して、現代人にも響くということは、人間に進歩がないのか、それとも普遍的な教示なのか。
本質は常にシンプルで、シンプルがゆえに忘れがちです。果たして自分はボスかリーダーか。改めて問いかけてみたいものです。
投稿者: